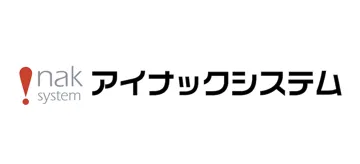提案したテーマについて
今回の提案テーマは「Smell Chain」構想です。これは、生産から消費者まで香りのデータを一括管理し、信頼性や付加価値を農産物に与える仕組みです。匂いセンサーとクラウドシステムを活用することで、農業や食品分野における新たな価値づくりに挑戦します。
提案内容について
農業の現場では、これまで熟練者の勘や経験に頼って品質が判断されてきました。例えば収穫のタイミングも「香り」で見極められることが多いのですが、これを数値化・データ化する手段はありませんでした。弊社の技術では、農産物の収穫適期や品質のばらつきを香りデータとして可視化し、消費者やバイヤーに客観的な指標として提示できます。これによって農産物の価値を正しく評価できるようになり、生産者の努力が公正に報われる仕組みを実現していきます。
弊社は「野菜の美味しさは味以上に香りにある」と考えています。例えばネギ一つをとっても、深谷ネギ、九条ネギ、一般的な青ネギでは香りが大きく異なります。これをセンサーで計測し、データとして表示することで、「味噌汁に合うネギ」「醤油に合うネギ」といった具体的な使い分けが可能になります。良し悪しだけでなく、多様な香りの個性を見える化することで、生産者は狙った品質を作りやすくなり、消費者も価格と品質を納得感を持って判断できるようになります。
すでに弊社の技術は食品メーカーや化粧品メーカーで導入が進んでおり、小麦粉のカビ検知やスパイスの産地判別、クラフトビールの開発・マーケティングにも活用されています。農業分野でも、高級メロン農家での実証実験を始めており、これまで人の鼻に依存して過小評価されていた香りの価値を、数値データとして正しく表現できるようになりました。香りを的確に評価できれば、スーパーでの売り分けや品種改良にも活用でき、農業の幅を広げる可能性があります。
DEEP VALLEY Agritech Award 2025に応募したきっかけは?
今回のアワードは、弊社のウェブサイトを通じてお声がけいただいたことをきっかけに応募しました。深谷市は農業に力を入れており、特産の深谷ネギをはじめ多品種が栽培されています。弊社の技術を導入することで、それぞれの作物が持つ香りの違いを可視化し、付加価値として提示することが可能になります。実際に深谷市の事務局も農業に詳しく、技術の社会実装を進めるにふさわしい地域だと確信しています。
今後は、深谷市の農産物を対象に香りデータの実証実験を行い、イチゴなどの主要作物にも技術を広げていく計画です。農産物の品質や魅力を香りデータで裏付けることができれば、輸出や販路拡大にも直結し、農業の構造そのものをアップデートできます。
この技術で深谷市とともに農業をアップデートし、未来へ進んでいきたいと考えています。香りはこれまで評価が難しい領域でしたが、数値化することで確かな付加価値を生み出せます。農業に新しい評価軸を導入する「匂いのDX」は、他社には真似できない挑戦です。最終審査では、深谷市の農業の可能性を最大限に引き出せる技術としてしっかりとお伝えし、次のステップに進めるよう臨みます。